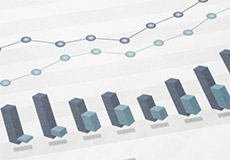ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン
ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンに向けた取組み
ダイバーシティ推進体制
2015年、ダイバーシティ環境の整備を求める社会的な要請が高まっているなかで、多様な人材が活躍できる職場づくりを更に強化するため人事部内に「人材活躍推進室」を設置しました。
人材活躍推進室では、「仕事と家庭の両立支援」や「女性の管理職への登用促進」といった女性活躍推進のほか、シニア・障がい者の活躍支援等、様々な世代、状況であってもやりがいを持って働ける職場づくりに取組んでいます。
女性活躍推進法に基づく行動計画
性別に関わらず、多彩な人材が活躍できる雇用環境を整備し、活躍推進を一層加速するために、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下、「女性活躍推進法」という)*」に基づく行動計画を策定し取り組んでいます。2023年4月1日付で、人材活躍推進に係る長期ビジョン「奏~SOU~」のステージⅠの期間中の取組みをふまえた第3期行動計画を策定しました。
<第3期行動計画の内容>
①管理職(課長職以上)に占める女性割合を20%以上にする。
- 取組み:
-
年齢・性別問わず期待する役割に応じた公正な処遇を実施する。
育成プログラムを実施し、キャリアアップや職務拡大へ繋げる。
②男性の育児休業(出生時育児休業を含む)取得率を100%以上にする。
- 取組み:
-
育休対象者に対する制度周知や計画的取得を徹底する。
育休取得促進に向けた組織風土を醸成する。
- * 女性の個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、国や地方公共団体、民間企業(一般事業主)に女性の活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や女性の職業選択に資する情報の公表を義務付けた法律です。
2016年、当行は女性活躍推進法の施行と同日に「女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業」として、埼玉労働局より認定証及び認定マーク「えるぼし」(4段階中上位2段階目)が授与されました。

女性の管理職登用に関する目標
2025年3月末現在、管理職(課長職以上)に占める女性割合は15.8%となっています。
2026年3月期の目標として、この数値を20%以上とすることを目指しています。
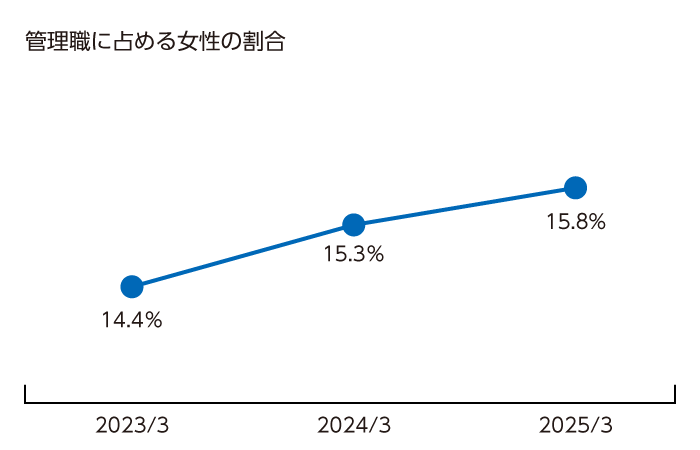
男女賃金格差是正のための取組み
2024年7月に実施した人事制度改正において総合職と特定職を統合したことで、コース間の賃金格差を是正いたしました。旧来の特定職の占める割合が高かった女性の活躍のフィールドを広げるとともに、賃金格差の是正も図っております。
| 2025年3月期実績 | |
|---|---|
| 男女賃金格差 |
全 体 54.7% 正 規 68.4% 非正規 63.8% |
キャリア形成のための取組み
行外研修への積極的な派遣や、TSUBASAアライアンス加盟行との「クロスメンター制度*」を通じて、女性のスキルアップやキャリア形成を支援しています。
* 「クロスメンター制度」とは
TSUBASA加盟行各行でメンター(相談を受ける人)、メンティ(相談をする人)をそれぞれ選出し、自行内の垣根を越えたメンタリング(対話・助言)を実施するもの。
地銀人材バンクの活用
全国64行で構成されている「輝く女性の活躍を加速する地銀頭取の会」に参加し、ネットワークを活かした取組みを行っています。結婚や介護などで転居するため退職せざるを得ない行員を転居先の銀行に紹介する「地銀人材バンク」制度を活用し、銀行員としてのキャリアの継続と働き続けられる環境を提供しています。
ぶぎんリターン制度
結婚・出産・育児・介護等家庭の事情で一旦退職した行員を、一定の条件を満たした場合に退職当時の条件で再雇用する制度です。在職時に培ったキャリアを再度発揮することを可能にしています。
アルムナイ採用
当行を退職した元行員を対象に再雇用するための制度です。「ぶぎんリターン制度」に比べ、退職理由や在職期間、離職期間等の条件を大幅に緩和しています。
「アルムナイ(*)」の方々に、退職後に培ったスキルや知見を発揮していただき、多様な価値観のなか、新たな気付きが生まれるような企業風土の醸成に繋げることを目指しています。
* アルムナイ(alumni)とは、英語で「卒業生」「同窓生」を意味する言葉です。
障がい者雇用の促進
働く障がい者、働くことを希望する障がい者の方々に働く喜びや生きがいを感じられる雇用の機会を提供できるよう、2017年「むさしのハーモニー株式会社」を設立し、2018年4月には「障がい者の雇用の促進等に関する法律」に基づく「特例子会社」として県内金融機関では初めての認定を受けました。
今後も、働く幸せを感じられるよう障がい者の方々が持っている能力を発揮し、いきいきと働くことのできる職場環境作りに努め、武蔵野銀行グループのCSR(社会的責任)を果たし地域社会に貢献してまいります。
なお、2024年3月末の障がい者雇用率は2.58%(民間企業の法定雇用率2.5%)となっています。
シニア層(キャリアマスター行員)の活躍推進
定年退職した行員の約8割が、定年後も引続き勤務しており、知識・経験を発揮し、監査、債権管理部門や営業店における新任課長の指導役など幅広い分野で活躍しています。一定の年齢毎に以下のように定年後の働き方やワークライフバランスについて考える機会を設け、定年後も安心して働けるよう、支援する体制を整備しています。
<シニア層に対する主な取組み>
| 対象となる年齢 | 支援体制 |
| 50歳 | 定年後の働き方を意識したライフプランを考える「キャリアデザイン研修会」 |
| 52歳・55歳・58歳 | 今後の働き方や自身のスキルの具体的な内容を銀行と刷り合わせ、イメージするための「キャリア面談」 |
| 60歳~65歳迄 | 定年後、知識や経験を活かし活躍する再雇用制度「キャリア・マスター行員制度」 |
| 65歳~70歳 | 引続き、知識や経験を活かす場を提供する「シニアパートナー制度」 |
仕事と家庭の両立支援に向けた主な取組み
出産・育児への各種支援
出産を望む従業員を支援するための「出生サポート休暇」をはじめ、法令を上回る育児休業制度や短時間勤務制度を設けているほか、本人の申出により残業せずに帰宅できる制度等を導入しています。また、育児休業期間中に行員専用サイト等による情報提供や、円滑な復職のための復帰前面談などを行う「職場復帰支援プログラム」を実施しています。
復帰後には、業務へのキャッチアップを支援するための「育休明け研修」、安心して働けるための「復職後面談」を実施しています。
男性の育児休業
男性の育児参加促進などを目的とした育児休業取得を推奨しており、育児休業の取得計画を早めに上司と共有する仕組を構築しています。配偶者の出産時には、部店長を介してお祝いメッセージを送付し、育児休業の取得を促しています。また、産後パパ育休の期間(子の出生後8週間)、育児休業の期間(子の出生後8週間以降)それぞれの取得開始初めの5営業日を有給としています。
≪育児休業等取得実績≫
| 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|
| 104.4% | 114.6% | 104.4% |
*男性の育児休暇取得率は、年度内に「育児休業等を取得した男性労働者数」を「配偶者が出産した男性労働者数」で除して算出しています。
*女性の育児休業取得対象者は、全員育児休業を取得しています。
介護に関する支援
介護に携わる従業員の負担軽減を目的とした自動車通勤許可基準の見直しや、介護に関する知識を習得することを目的としたセミナーを定期的に開催しています。
ワーク・ライフ・バランス実践ハンドブック(育児編・介護編)
従業員一人ひとりが、仕事と育児・介護の両立に向けて、さまざまな制度や仕組、考え方を理解するための内容を盛り込んだハンドブックを作成し、全従業員が自宅でも自由に閲覧し、必要に応じて活用できるよう、行員専用サイトへ掲載しています。
【当行のライフステージの変化に対応するための両立支援諸制度】
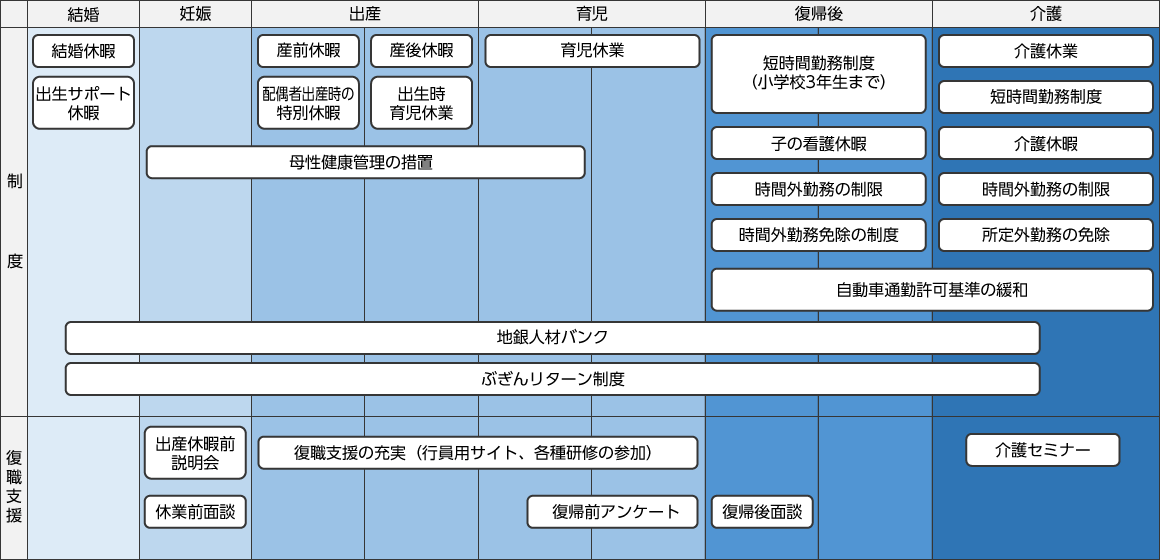
当行では、次世代育成支援に向けた「行動計画」を策定しており、2010年および2015年の2回にわたり埼玉労働局から次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受け、認定マーク「くるみん」を取得しました。さらに、2017年には子育てサポート特例認定企業として、認定マーク「プラチナくるみん」を県内金融機関としては初めて取得しています。

年次有給休暇の計画的取得の促進
従業員が仕事と私生活をともに大切にしながら意欲的に働けるよう、年次有給休暇を計画的に取得するための制度休暇(連続休暇、計画休暇、ワークライフバランス休暇)を定めています。
| 休暇名 | 休暇取得できる期間 |
連続休暇 |
連続した7日間(土日祝日を利用して最長10日間可能) |
計画休暇 |
連続した3日間(土日祝日を利用して最長6日間可能) |
リフレッシュ休暇 |
勤続満10年:土日祝日を利用して最長11日間 |
ワークライフバランス休暇 |
半期に2日、合計年間4日間(勤続1年以上) |