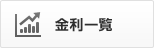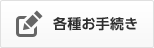�l�I���{�o�c�̎��H�`�����r�W�����uMCP�v�����Ɍ�����
�������s�ł́A�l�I���{��������Ɖ��l�̌���ł���Ƃ����F���̂��ƁA���l�Ȑl�ނ̊������i���d�v�Ȍo�c�헪�̈�ƈʒu�Â��A��l�ЂƂ�̐�含�����߂�l�ވ琬�̍��x���ɒ��͂���Ƌ��ɁA�_�C�o�[�V�e�B&�C���N���[�W�����ȂǑS�Ă̏]�ƈ�������ł���E����̐����ɓw�߂Ă��܂��B�_�C�o�[�V�e�B���i��ʂ��A�]�ƈ���l�ЂƂ�̑��l������������A�S�����P�����s��ڎw���A�ϋɓI�Ɏ��g��ł��܂��B
2023�N3���ɍ��肵�������r�W�����uMCP�iMusashino mirai-Creation Plan�j�v�ł́A�u�n��E���q���܂̊��҂��鑶�݂ցv�u�g�D�E�]�ƈ��̗͂��ő剻�v�Ƃ�����{���j���f���Ă��܂��B���̊�{���j�Ɋ�Â��A���߂���l�ނ���ёg�D�ɂ��āA���ꂼ��u�����E����v�u���l���E�Ȃ���v�Ƃ����L�[���[�h��ݒ肢�����܂����B
�]�ƈ��̐����Ƃ��܂��܂ȂȂ����ʂ��A�����r�W�����ŕW�Ԃ���u���ʂȉ��l�����W���A�n�懂1�̃\�����[�V�����ō�ʂ̖������v���������ׂ��A�l�I���{�o�c�̎��H�ɓw�߂Ă��܂��B
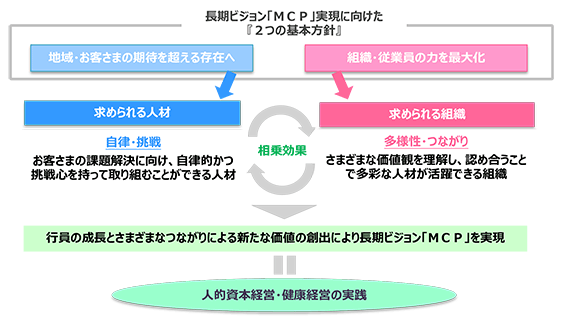
�l�ވ琬���j
���s�́A�u�����v�u����v�̃L�[���[�h�̂��ƁA�n��E���q���܂̊��҂��z���鑶�݂ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���A�L���Ȓn��Љ�̖����̎����Ɍ����Ď��g�߂�l�ނ��琬���Ă܂���܂��B
| ���� | �s�m�����̍�������ɂ����āA�]�ƈ���l�ЂƂ肪����̍l������v���Ɋ�Â��s���E���f�ł���悤�A��������g�ɂ����l�ނ��琬���Ă܂���܂��B |
|---|---|
| ���� | �]�ƈ���l�ЂƂ肪�A�ڂ̑O�ɂ��邳�܂��܂ȋ@��ɑ��A����ӎv�\�����A�`�����X��͂����Ƃ��钧��S���������l�ނ��琬���Ă܂���܂��B |
�����������j
���s�́A�u���l���v�u�Ȃ���v�̃L�[���[�h�̂��ƁA�g�D�Ə]�ƈ��̗͂̍ő剻�Ɍ����A���ω��ɑΉ����邽�߂Ƀ��W���G���X�����߂�Ƌ��ɁA���l�ȓ�������ł���Г�����z���Ă܂���܂��B
| ���l�� | �]�ƈ���l�ЂƂ肪�ڕW�⓭�����������o������ŁA�����̗͂��ő�������ł���悤�A�u���ʂȍl�����𗝉����A���݂��ɔF�ߍ����A���d�ł���A�S���I���S���̍����E���z���Ă܂���܂��B |
|---|---|
| �Ȃ��� | �u���l�ς̈قȂ�ғ��m�v���A���܂��܂Ȍ`�̂Ȃ����z���A�ЂƂ�ł͐������Ȃ��V���ȉ��l�����o�����Ƃ̂ł����Ƃ�ڎw���Ă܂���܂��B |
�l�ފ������i�ɌW�钷���r�W�����u�t�`SOU�`�v�̐���
���ʂ�N��ɂ������Ȃ��A���l�Ȑl�ނ����Ă������Ƃ��A��Ƃ̋����͂����߁A�V���ȉ��l�ݏo������ƂȂ�Ƃ̍l���̂��ƁA2023�N4�����u�l�ފ������i�Ɋւ����{���j�v�y�ѐl�ފ������i�ɌW�钷���r�W�����u�t(����)�`SOU�`�v�𐧒肢�����܂����B
1.�����r�W�����̊T�v
�]�ƈ���l�ЂƂ肪�قȂ�������A���݂��ɂ��̈Ⴂ��F�ߍ����A���͂��A�x�N�g�������킹�A�g�D�̎����I���W�֊�^���Ă������Ƃ�ڎw�����߁A�l�ފ������i�ɌW�钷���r�W�����u�t�`SOU�`�v�𐧒肵�A2023�N�x����2032�N�x��10�N�ԂŎ����Ɍ����Ď��g��ł��܂��B
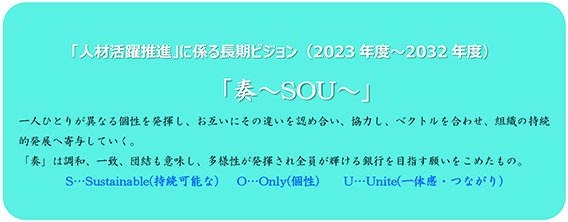
2.���̂ɂ���
![]()
��l�ЂƂ肪�قȂ�������A���݂��ɂ��̈Ⴂ��F�ߍ����A���͂��A�x�N�g�������킹�A�g�D�̎����I���W�֊�^���Ă������Ƃ�\�����܂����B�u�t�v�͒��a�A��v�A�c�����Ӗ����A���l������������S�����P�����s��ڎw���肢�����߂Ă��܂��B
3.��{���j�E10�N�Ԃ̖ڎw���p
�u�t�`SOU�`�v�́A��w�̐l�ފ������i��ʂ��A�����r�W�����uMCP�v�̎�����ڎw���Ă������̂ƈʒu�t���Ă���A�uMCP�v��2�̊�{���j�ɑΉ����A�u�����E����v�A�u���l���E�Ȃ���v�Ƃ����L�[���[�h�̂��ƁA�l�ނ���ёg�D�̖ڎw���ׂ��p�Ƃ��āu���q���܂̉ۑ�����Ɍ����A�����I������S�������Ď��g�ނ��Ƃ��ł���l�ނ��琬����v�A�u���܂��܂ȉ��l�ς𗝉����A�F�ߍ������Ƃő��ʂȐl�ނ�����ł���g�D�����v���A��{���j�Ƃ��Čf���Ă��܂��B
�����̎����Ɍ����A2023�N�x�����10�N�Ԃ�3�̃X�e�[�W�ɕ����A�e�X�e�[�W�̖ڎw���p���߂Ď��g�ނ��ƂŁA10�N��ɂ́A���l�Ȑl�ނ����M�ɖ������A�\�͂��ő���ɔ����ł���g�D��ڎw���Ă��܂��B
�i1�j��{���j
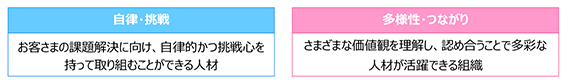
�i2�j10�N�ԂŖڎw���p
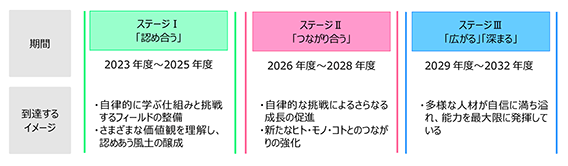
�_�C�o�[�V�e�B&�C���N���[�W�����Ɍ�������g��
�_�C�o�[�V�e�B���i�̐�
2015�N�A�_�C�o�[�V�e�B���̐��������߂�Љ�I�ȗv�������܂��Ă���Ȃ��ŁA���l�Ȑl�ނ�����ł���E��Â�����X�ɋ������邽�ߐl�������Ɂu�l�ފ������i���v��ݒu���܂����B
�l�ފ������i���ł́A�u�d���Ɖƒ�̗����x���v��u�����̊Ǘ��E�ւ̓o�p���i�v�Ƃ����������������i�̂ق��A�V�j�A�E�Ⴊ���҂̊���x�����A�l�X�Ȑ���A�ł����Ă���肪���������ē�����E��Â���Ɏ�g��ł��܂��B
�����������i�@�Ɋ�Â��s���v��
���ʂɊւ�炸�A���ʂȐl�ނ�����ł���ٗp�������A�������i����w�������邽�߂ɁA�u�����̐E�Ɛ����ɂ����銈��̐��i�Ɋւ���@���i�ȉ��A�u�����������i�@�v�Ƃ����j���v�Ɋ�Â��s���v������肵���g��ł��܂��B2023�N4��1���t�ŁA�l�ފ������i�ɌW�钷���r�W�����u�t�`SOU�`�v�̃X�e�[�W�T�̊��Ԓ��̎�g�݂��ӂ܂�����3���s���v������肵�܂����B
����3���s���v��̓��e��
�@�Ǘ��E�i��C�ȏ�j�ɐ�߂鏗��������30���ȏ�ɂ���B
- ��g�݁F
- �N��E���ʖ�킸���҂�������ɉ����������ȏ��������{����B
�琬�v���O���������{���A�L�����A�A�b�v��E���g��q����B
�A�j���̈玙�x�Ɓi�o�����玙�x�Ƃ��܂ށj�擾����100���ȏ�ɂ���B
- ��g�݁F
- ��x�Ώێ҂ɑ��鐧�x���m��v��I�擾��O�ꂷ��B
��x�擾���i�Ɍ������g�D���y����������B
- �������̌��Ɣ\�͂��\���ɔ����ł���Љ���������邽�߂ɁA����n�������c�́A���Ԋ�Ɓi��ʎ��Ǝ�j�ɏ����̊������i�Ɍ��������l�ڕW�荞�s���v��̍���E���\�⏗���̐E�ƑI���Ɏ�������̌��\���`���t�����@���ł��B

2016�N�A���s�͏����������i�@�̎{�s�Ɠ����Ɂu�����̊������i�Ɋւ����g�̎��{�����D�ǂȊ�Ɓv�Ƃ��āA��ʘJ���ǂ��F��؋y�єF��}�[�N�u����ڂ��v�i�ō��ʁj�����^����܂����B
�����̊Ǘ��E�o�p�Ɋւ���ڕW
2023�N3�������݁A�����̊Ǘ��E�i��C�ȏ�j�ɐ�߂鏗��������25.3���ƂȂ��Ă��܂��B
2025�N�x�ɂ́A���̐��l��30���ȏ�Ƃ��邱�Ƃ�ڎw���Ă��܂��B
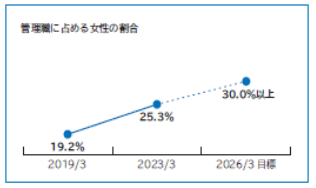
�L�����A�`���̂��߂̎�g��
�����̃L�����A�`���x����l�b�g���[�N�\�z��ړI�Ƃ������C��A�����E�����N���X�ƈ�Έ�Ŗʒk����L�����A�f�B�X�J�b�V�����Ȃǂ��J�Â��Ă��܂��B�܂��A�s�O���C�ւ̐ϋɓI�Ȕh���ɂ��A�����̃X�L���A�b�v��X�e�b�v�A�b�v��}���Ă��܂��B
�n��l�ރo���N�̊��p
�S��64�s�ō\������Ă���u�P�������̊������������n�⓪��̉�v�ɎQ�����A�l�b�g���[�N������������g�݂��s���Ă��܂��B��������Ȃǂœ]�����邽�ߑސE������Ȃ��s����]����̋�s�ɏЉ��u�n��l�ރo���N�v���x�����p���A��s���Ƃ��ẴL�����A�̌p���Ɠ����������������Ă��܂��B
�Ԃ��^�[�����x
�����E�o�Y�E�玙�E��쓙�ƒ�̎���ň�U�ސE�����s�����A���̏����������ꍇ�ɑސE�����̏����ōČٗp���鐧�x�ł��B�ݐE���ɔ|�����L�����A���ēx�������邱�Ƃ��\�ɂ��Ă��܂��B
�Ⴊ���Ҍٗp�̑��i
�����Ⴊ���ҁA�������Ƃ���]����Ⴊ���҂̕��X�ɓ�����т����������������ٗp�̋@���ł���悤�A2017�N�u�ނ����̃n�[���j�[������Ёv��ݗ����A2018�N4���ɂ́u�Ⴊ���҂̌ٗp�̑��i���Ɋւ���@���v�Ɋ�Â��u����q��Ёv�Ƃ��Č������Z�@�ւł͏��߂Ă̔F����܂����B
������A�����K������������悤�Ⴊ���҂̕��X�������Ă���\�͂����A���������Ɠ������Ƃ̂ł���E������ɓw�߁A�������s�O���[�v��CSR�i�Љ�I�ӔC�j���ʂ����n��Љ�ɍv�����Ă܂���܂��B
�Ȃ��A2023�N3�����̏Ⴊ���Ҍٗp����2.43���i���Ԋ�Ƃ̖@��ٗp��2.3���j�ƂȂ��Ă��܂��B
�V�j�A�w�i�L�����A�}�X�^�[�s���j�̊������i
��N�ސE�����s���̖�8�����Čٗp�҂Ƃ��ċΖ����Ă���A�m���E�o�������A�č��A���Ǘ������c�ƓX�ɂ�����V�C�ے��̎w�����ȂǕ��L������Ŋ��Ă��܂��B���̔N��Ɉȉ��̂悤�ɒ�N��̓�������[�N���C�t�o�����X�ɂ��čl����@���݂��A��N������S���ē�����悤�A�x������̐������Ă��܂��B
���V�j�A�w�ɑ����Ȏ�g�݁�
| �ΏۂƂȂ�N�� | �x���̐� |
| 48�� | �d����o���̒I�������s�����Ƃɂ��A����̃L�����A�ɂ��čl����u�Z�J���h�L�����A���C��T�v |
| 50�� | ��N��̓��������ӎ��������C�t�v�������l����u�Z�J���h�L�����A�f�U�C�����C��U�v |
| 52�E55�E58�� | ����̓������⎩�g�̃X�L���̋�̓I�ȓ��e����s�ƍ��荇�킹�A�C���[�W���邽�߂́u�L�����A�ʒk�v |
| 60�`65�Ζ� | ��N��A�m����o��������������Čٗp���x�u�L�����A�E�}�X�^�[�s�����x�v |
| 65�`70�� | �������A�m����o����������������u�V�j�A�p�[�g�i�[���x�v |
�d���Ɖƒ�̗����x���Ɍ�������Ȏ�g��
�o�Y�E�玙�ւ̊e��x��
�o�Y��]�ޏ]�ƈ����x�����邽�߂́u�o���T�|�[�g�x�Ɂv���͂��߁A�@�߂�����玙�x�Ɛ��x��Z���ԋΖ����x��݂��Ă���ق��A�{�l�̐\�o�ɂ��c�Ƃ����ɋA��ł��鐧�x�������Ă��܂��B�܂��A�玙�x�Ɗ��Ԓ��ɍs����p�T�C�g���ɂ�����A�~���ȕ��E�̂��߂̕��A�O�ʒk�Ȃǂ��s���u�E�ꕜ�A�x���v���O�����v�����{���Ă��܂��B
���A��ɂ́A�Ɩ��ւ̃L���b�`�A�b�v���x�����邽�߂́u��x�������C�v�A���S���ē����邽�߂́u���E��ʒk�v�����{���Ă��܂��B
�j���̈玙�x��
�j���̈玙�Q�����i�Ȃǂ�ړI�Ƃ����玙�x�Ǝ擾�𐄏����Ă���A�玙�x�Ƃ̎擾�v��𑁂߂ɏ�i�Ƌ��L����d�g���\�z���Ă��܂��B�z��҂̏o�Y���ɂ́A���X������Ă��j�����b�Z�[�W�𑗕t���A�玙�x�Ƃ̎擾�𑣂��Ă��܂��B�܂��A�Y��p�p��x�̊��ԁi�q�̏o����8�T�ԁj�A�玙�x�Ƃ̊��ԁi�q�̏o����8�T�Ԉȍ~�j���ꂼ��̎擾�J�n���߂�5�c�Ɠ���L���Ƃ��Ă��܂��B
��o�Y�ҁE�z��ҏo�Y�҂ɐ�߂�玙�x�Ɠ��擾���с�
| 2018�N�x | 2019�N�x | 2020�N�x | 2021�N�x | 2022�N�x | |
|---|---|---|---|---|---|
���� |
100�� | 89.5�� | 102.2�� | 111.9�� | 89.5�� |
�j�� |
71.9�� | 100�� | 84.8�� | 84.8�� | 104.4�� |
�玙�x�Ǝ擾�����N�x���Ɉ玙�x�Ƃ��擾�����l���^�N�x���Ɏq�����܂ꂽ�l��
���Ɋւ���x��
���Ɍg���]�ƈ��̕��S�y����ړI�Ƃ��������Ԓʋ���̌�������A���Ɋւ���m�����K�����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����Z�~�i�[�����I�ɊJ�Â��Ă��܂��B
���[�N�E���C�t�E�o�����X���H�n���h�u�b�N�i�玙�ҁE���ҁj
�]�ƈ���l�ЂƂ肪�A�d���ƈ玙�E���̗����Ɍ����āA���܂��܂Ȑ��x��d�g�A�l�����𗝉����邽�߂̓��e�荞�n���h�u�b�N���쐬���A�S�]�ƈ�������ł����R�ɉ{�����A�K�v�ɉ����Ċ��p�ł���悤�A�s����p�T�C�g�f�ڂ��Ă��܂��B
�y���s�̃��C�t�X�e�[�W�̕ω��ɑΉ����邽�߂̗����x�������x�z
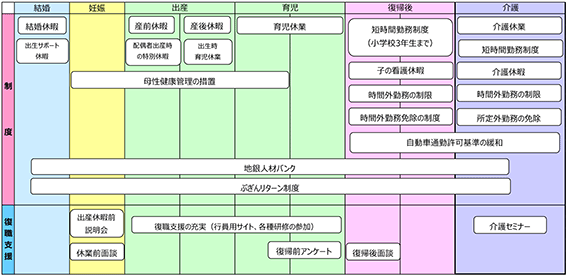

���s�ł́A������琬�x���Ɍ������u�s���v��v�����肵�Ă���A2010�N�����2015�N��2��ɂ킽���ʘJ���ǂ��玟����琬�x�������i�@�Ɋ�Â��F����A�F��}�[�N�u����݂�v���擾���܂����B����ɁA2017�N�ɂ͎q��ăT�|�[�g����F���ƂƂ��āA�F��}�[�N�u�v���`�i����݂�v���������Z�@�ւƂ��Ă͏��߂Ď擾���Ă��܂��B
�N���L���x�ɂ̌v��I�擾�̑��i
�]�ƈ����d���Ǝ��������Ƃ��ɑ�ɂ��Ȃ���ӗ~�I�ɓ�����悤�A�N���L���x�ɂ��v��I�Ɏ擾���邽�߂̐��x�x�Ɂi�A���x�ɁA�v��x�ɁA���[�N���C�t�o�����X�x�Ɂj���߂Ă��܂��B
| �x�ɖ� | �x�Ɏ擾�ł������ |
�A���x�� |
�A������7���ԁi�y���j���𗘗p���čŒ�10���ԉ\�j |
�v��x�� |
�A������3���ԁi�y���j���𗘗p���čŒ�6���ԉ\�j |
���t���b�V���x�� |
�Α���10�N�F�y���j���𗘗p���čŒ�11���� |
���[�N���C�t�o�����X�x�� |
������2���A���v�N��4���ԁi�Α�1�N�ȏ�j |